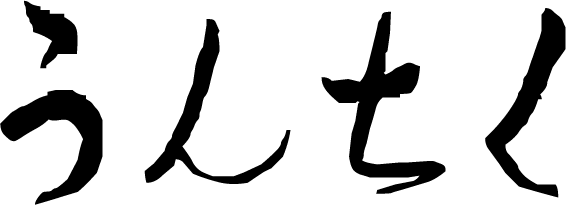みなさん、カルト映画はお好きだろうか。「好きか嫌いかで言えばあまり好きじゃない。というか観たことない。そもそもカルト映画ってなに?」という方も多いのではないかと思う。
カルト映画とは“一部の熱狂的なファンに支持される映画”のことをいう。言葉の雰囲気からしてなにやら不吉な感じが……たとえば、グロテスク、血みどろ、とにかく痛い、なんで映像化した?など、いろいろと感じることがあるかと思う。
しかし、ご安心を。今回筆者が考察していく映画『エンドレス・ポエトリー』は、カルト映画の巨匠アレハンドロ・ホドロフスキーの監督作ではあるが、カルト映画ではない。これは一部の熱狂的なファンのためのものではなく、多くの人に開かれた救いの映画なのである。
当記事は、映画『エンドレス・ポエトリー』に “衝撃を受けつつ癒され救われた”という筆者の体験を、初期代表作『エル・トポ』と対比しながら、神話、宗教、哲学の言葉をまじえて解説していくものである。
はじめに、ホドロフスキーとは何者か
『エンドレス・ポエトリー』について述べる前に、まずはホドロフスキーがどんな人物かを知っていただこう。
御年88歳、金を失うために映画を作る
日本で言えば米寿のホドロフスキー。すでに次回作の脚本を書き始めており、あと3本5本の映画を撮りたいとも言っている。なんという精神、肉体であろうか。
また映画監督だけではなく、演劇家、バンド・デシネ(フランスのコミック)原作者でもあり、サイコマジック(ホドロフスキー考案の精神療法)やタロットリーディングなどの活動も行っている。実に多彩。
私は金のために映画を作らない。金を“失う”ために映画を作るんだ。
これは『ブラック・スワン』の監督ダーレン・アロノフスキーとの対談での言葉だ。ホドロフスキーは常々、”映画は芸術であるべきなのにハリウッドはビジネスを生み出すだけだ”と言及している。
カルト映画の巨匠と言わしめた『エル・トポ』
代表作『エル・トポ』(1970)は、メキシコを舞台とした西部劇(この時点で妙)という体裁をとった精神劇だ。暴力、惨殺、宗教、同性愛、奇形、近親相姦、秘密結社など、世界のタブーをこれでもかというほど露呈し、人間の善と悪に血肉を注いで向き合った映画である。
その特異性は、ジョン・レノンが惚れ込んで配給権を買い取ったことや、劇中のウサギの死体はすべて本物であり、しかもそれはホドロフスキー自身が一匹一匹殴り殺したという逸話からもうかがえる。
筆者はこれを、なんら説明もなく友人から薦められ、DVDにて鑑賞した。はじめは「ああ、西部劇か」くらいに思ったが、すぐに異変に気づいた。まず子供が裸で変、次いでカメラは内臓の見えた動物の死体と白衣を纏った人間の惨殺光景、血の溜りをとらえ、それが乾き切ったメキシコの白昼で繰り広げられていく。そういうことがバシバシと続いていく。一度観ただけでは理解しがたい内容なのだが、恐怖につき二度目の鑑賞はだいぶあとになってからである。
生きることを全肯定した『エンドレス・ポエトリー』
ざっくりではあるが、ホドロフスキーという人物に対するイメージを読者のみなさんと共有できたのではないかと思う。さて、ここからが本題だ。
『エンドレス・ポエトリー』は、ホドロフスキー自身の自伝的映画である。父との軋轢、悲しみや葛藤を抱えたホドロフスキー青年が、アバンギャルドな詩人やアーティストなどとの出会いを経て、精神的・環境的囚われから解放され、詩人としての自己を確立していく物語である。
以下、劇中のセリフ。
__自分を生きるのは罪じゃない。他人の期待どおりに生きるほうが罪だ。
人生の意味は?
__人生か。頭は質問するが、心は答えを知ってる。意味などない、生きるだけだ。
このどストレートなセリフから感じるとおり、本作は「生きること」を全肯定する青春映画だ。物語的にもまっとうな終着点も持っている。ホドロフスキーはこの物語を詩的な映像美で描いていくわけだが、そこにホドロフスキーらしさが炸裂していくのである。
彼の詩的な映像美はまったくやさしくない。極彩色にサイケでエロティック、やはり予定調和は微塵もなく「え?え!?」の繰り返し。映像は『エル・トポ』のように残虐ではないのに、なんだか怖い。理性をどんどん削がれ、穏やかに自分を失っていく感じだ。だからもう「意識」で受け止めるのはお手上げとなり、次第に「無意識」で受け止めるようになる。そしていつのまにかルールのない幻想世界に入り込み、”そこで起こっていることが真実なのだ”と感じるようになっていく。
鑑賞後に感じたのは“救い”
意識が通用しない場所は怖い。自己をコントロールできなくなるからだ。しかし鑑賞後には「あ、生きよう」と真っ直ぐに思い、救われている自分に気づく。これはなんだ?精神的衝撃体験だ。鑑賞後、筆者は居ても立ってもいられない気分だった。
たとえば、作家・町田康氏は本作に対して以下のコメントを寄せている。
(前略)私たちはどうやったら前向きに生きられるの?その答えがこの映画のなかにありました。(中略)生きようと思いました。
大げさでもなんでもなく、本当にそんな感じなのだ。
ホドロフスキーはこの映画をサイコマジック・ボムとも呼んでいる。サイコマジック・ボムとは、精神を変容させる衝撃とでも言い換えられるだろうか。ホドロフスキーは「意識を破壊し、無意識を覚醒させ、そこに生まれてきたものを直視せよ」と言い、見事にそれを観客に体験させた。わずか2時間のあいだに、だ。
神話、宗教、哲学から考察してみた

この衝撃、癒しと救いはなんだろう。見識者の言葉を探ってみた。
インド神話に登場するシヴァは「すべてを破壊し、新たに再生する神」。ここでいう破壊とは、憎しみや怒り、罪のためではなく、新しく再生するための破壊である。
日本の宗教学者であり、国立民族学博物館名誉教授の立川武蔵氏が編著した書籍『癒しと救い−アジアの宗教的伝統に学ぶ』(2001)には以下の一節がある。
ほとんどの人が自由、光、晴れやかな気持ちというような肯定的な状況に至る前に、魂の暗い領域の探求へ入り、そこを通過していかなければならない
そして2017年、オーストラリア・アデレード大学の哲学者クリス・レスビー氏は、「ドラッグ(幻覚剤)使用時が『正気』であり、通常時が『幻覚』である」という驚きの論文を発表した。
ふうむ。どうやら人は太古から今に至るまで、また国を超えて、案外共通した考えを持っているようだ。再生のために破壊して、魂の暗い領域を通過し、幻覚世界で真の自分に出会う。それと同時に、これらの言葉は日常があるがゆえに生まれたものだとも実感する。この映画が多くの人の救いになると筆者が感じたのは、多くの人がそれぞれの日常を必ず持っているからだ。そして日常はいつも、少なからず私たちを閉じ込め、不自由にしている。つまり誰もが、救いを必要としているのだ。
劇場へ!上映情報
百聞は一見にしかず。『エンドレス・ポエトリー』は、2017年1月現在も全国のミニシアター系で上映中だ。いくつかのシアターでは『エル・トポ』など過去6作品も鑑賞できる「ホドルフスキー特集」も開催中である。
上映情報はこちら。
読者のみなさんそれぞれのエンドレス・ポエトリー……終わりなき詩がどうか見つかりますように。素直に強く、そう思います!