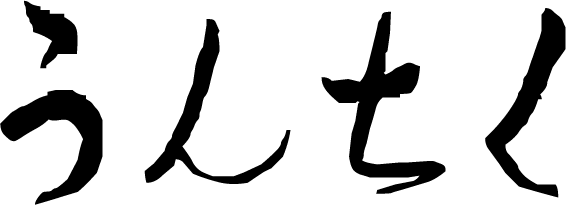映画やアニメに出てくる食べ物に思わず喉がごくりと動く、という経験をしたことのある人も多いと思います。私の場合は、ジブリ映画『天空の城ラピュタ』でパズーが食べていた目玉焼きのパンや、洋画に出てくるテイクアウトの紙のランチボックスにずっと憧れていました。
もちろん、小説内で出てくる食べ物も、言わずもがなです。文字だけで表された食べ物に、ふと湯気や匂いが立ちこめてくるような瞬間があり、「ああ、私は食べ物が美味しそうに描写された小説が好きだなあ」とよく思います。なかでも、作家である川上弘美さんの小説に出てくるごはんや肴には、いつも食欲を刺激されます。
当記事では、そんな川上弘美さん作品の魅力を、作中に登場する食べ物にフォーカスしながら紹介したいと思います。
【1】『センセイの鞄』
あらすじ
37歳独身のツキコがひとりで通う居酒屋で隣り合ったのは、高校のときの国語のセンセイだった。70歳を超えて初老となったセンセイとは肴の好みがよく合い、自然と往来するようになる。春に花見をしたり、秋にはきのこ狩りをしたり。二人はときに些細な喧嘩もしながら、巡る季節を愛でるように、ゆっくりと恋情を育んでいく――。
ツキコの実家の「湯豆腐」
この小説には美味しそうな食べ物がたくさん出てくるのですが、私がいちばん惹かれるのはツキコの実家の湯豆腐です。
醤油を酒で割って削りたてのかつぶしを散らしたものを、小さな湯のみに入れ、豆腐と一緒に土鍋の中で温める。じゅうぶんにあたたまった土鍋の蓋をあけると、湯気がほんわりとあがる。切らずに丸のまま温められた、ごつごつと目のつんだ木綿豆腐を、箸の先でくずす。角のお豆腐屋さんのお豆腐でなければだめなの。
湯豆腐は断然、木綿だなと思います。木綿豆腐を箸で割りながら、ぼろぼろ崩れてきたところと、薬味をうまく掬って食べるのが、なんだか美味しいと思うのです。
ツキコは湯豆腐が好きで、居酒屋でも頼むし自分でも作ります。自分で作るのには豆腐しか入れませんが、センセイの作った湯豆腐には、鱈と春菊が入っていました。鱈と春菊が入った湯豆腐を食べながら、ツキコは「こうして知らない同士が馴染んでゆくのだな」と思い、鱈にくっついてきた春菊を見て、白と緑がきれいだと感動します。
ほんわりとあがる湯気に、じわりと帯びていく酒気に、何もかもが愛おしいと思える瞬間に、読んでいる方の頬もほのかに紅潮する一冊です。
【2】『蛇を踏む』
あらすじ
珠数屋「カナカナ堂」に勤務するヒワ子は、籔で蛇を踏んでしまった。「踏まれたらおしまいですね」と蛇は言い、どろりと溶けてかたちを失ってから、もう一度「おしまいですね」と言って人間のかたちになった。蛇は50歳くらいの女のような姿で「踏まれたので仕方ありません」と言って、ヒワ子の家の方へ姿を消した。
ヒワ子が仕事を終えて家に帰ると、女が料理を作って待っていた。ヒワ子は直感的に「蛇だ」と思う。女は「あなたのお母さんよ」と言って棲みついた。追い出すでもなく懐くわけでもなく暮らしていると、珠数屋の奥さんニシ子さんも蛇に憑かれているし、珠数屋の得意先のお坊さんの女房も蛇だという。ヒワ子の家に棲みついた蛇は、やがてヒワ子を蛇の世界に誘うようになる――。
蛇が作った「つくね団子といんげんを煮たもの」
ヒワ子が蛇を踏んだ日、家に帰ると女に化けた蛇が料理を作って待っています。ビールと供されたのは、つくね団子といんげんを煮たものに、刺身におから。ヒワ子は、蛇のつくった刺身に気味悪さを覚えるものの、美味しそうなつくねに箸をつけます。
気味が悪かったが、つくねがおいしそうなので私も皿に取った。女はどんどん食べる。少しだけ箸でつついて汁が出たので、つい食べた。
つくねにビールだけでも十分に美味しそうなのに、いんげんが一緒というのが、にくいなと思うのです。動物性たんぱく質と一緒に甘辛く味付けした野菜の美味しさ。ぶり大根、いかと里芋の煮物にチンジャオロース。そういったものを食べているときに感じる、「果たして主役はどっちなのか」という疑問は、日常と非日常がぐるんと反転するような川上弘美さんの小説と相通ずるような気がします。
日常というものはつくね団子のように、一見しただけではわからない様々なものを内包しています。そして私たちは、そんなわかったようなことを思った矢先、添えられたいんげんの旨味に感動して、また少し途方に暮れます。それでも、またつくねを箸でつつけば美味しそうで、私たちは箸をつけずにいられないのです。そんな、たやすく揺れ動く主体が描かれた一冊です。
【3】『いまだ覚めず』
あらすじ
短編集『おめでとう』に収録されている『いまだ覚めず』。主人公の「あたし」は、かつて恋仲だったタマヨさんに10年ぶりに会いに行く。タマヨさんは知らない男と結婚して、三島に行ってしまった。時間とともに変容する恋愛感情や憎悪や自分の姿。「あたし」はずっと強情を張っていたのだけれど、やっぱりタマヨさんのことが好きなのだった――。
相模湾でとれた「生の蛸」
生の蛸を食べさせる店で、相模湾でとれるという何種類かの蛸を出された。タマヨさん、あいしてる、そう言うと、タマヨさんは蛸をむつむつ噛んだ。タマヨさんが噛むとあたしも食べたくなった。あいしてる、と言うのはお休みにして、蛸に専念した。
私にとって生蛸は、食べたいものとしてすぐに浮かんでくるものではないのですが、居酒屋や寿司屋で「生蛸」と見たら、頼まずにいられない逸品です。生蛸を食べた私は、「ああ美味しい」と舌鼓を打つものの、その感動はすぐに記憶のどこかへと追いやられてしまいます。
生蛸は本当に美味しいのか、私は生蛸が本当に好きなのか――。それはよくわかりません。ただ、食べたときには「ああやっぱり生蛸が好きだなあ」と思います。都合よく「やっぱり」などと思うのです。それでも「ああ美味しい」という気持ちに嘘はありません。
タマヨさんに「あいしてる」と言う「あたし」の気持ちにも、嘘はありません。ただ、そう言葉にしてしまうまでには、紆余曲折、悲喜交交があります。人の記憶は、都合よく変化するものなのです。そんな複雑さや、失恋の切なさや滑稽さを、「むつむつ」というオノマトペの奥に潜ませた一篇です。
味わい深い川上弘美作品の数々
今回は3つの食べ物と3つのお話に絞ってご紹介しましたが、川上弘美さんの小説にはまだまだたくさんの美味しそうなものが登場します。実際に美味しいお店を探すのも楽しいですが、たまにはこんな視点で小説を探してみるのもいかがでしょうか。