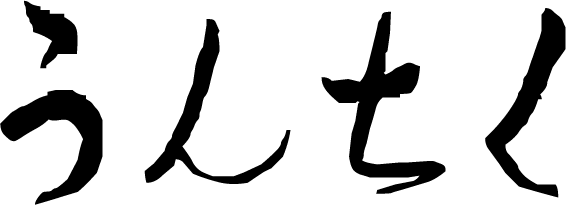今や世界第二位の経済大国として繁栄を謳歌する中国ですが、その裏には、一党独裁による人権と自由抑圧の暗い歴史を秘めています。外部からはうかがい知ることのできない「閉じた国」であった文化大革命の時代の中国から現在の中国に至るまで、中国と中国の人々の感性はどのように発露され、表現されてきたのでしょうか。それを知る手段として、中国映画と中国の発展の歴史を、長年の中国映画ウォッチャーである筆者が概観します。
文化大革命の時代の中国は得体のしれない国であった
「文化大革命」と言われても「それって何?」と思う人が多いのではないでしょうか。逃亡犯条例の改正案をめぐる抗議デモで揺れる現在の香港で、コメンテーターなどの話題にたびたび上るのが、東西冷戦終結の年1989年に中国の北京で起きた天安門事件です。西のベルリンの壁崩壊と同時期に、東の天安門事件が起きました。そこからさかのぼること23年前の1966年から1976年までの10年もの間、中国全土を揺るがした「プロレタリア文化大革命」いわゆる“文革”のことは、現地の中国人を含めて、人々の遠い記憶の彼方に消え去っているかのように思えます。
当時の中国は、日本からは遠い国でした。我々の知り得る中国は、ラジオに耳を当てると聞こえてくる雑音だらけの北京放送から、日本語を拾い聞きして想像を膨らませることしかできない得体のしれない国であり、人民服と人民帽に身を包んだ紅衛兵が、毛沢東語録を片手に「造反有理!」と叫んでいる姿が、大方の日本人が中国について描いているイメージでした。今の北朝鮮と同じで、普通の生活や普通の感情が交錯する日常が存在するとは、とても想像できない世界だったのです。
当時の中国映画で日本でも見ることができたのは『紅色経典』(共産主義模範作品)として公開された『紅色娘子軍』(1970年制作)くらい。大仰で芝居がかったプロパガンダに終始する革命劇という実態とは裏腹に、「紅色」という語感から妙にエロティックな妄想を抱かせるものでした。
しかし、その頃にも、今とは比較にならないほどの少数ですが、中国人が日本に住んでいました。村上春樹の初期の短編『中国行きのスロウ・ボート』には、語り手の思い出の中にある三人の中国人とのエピソードが描かれ、村上の初期の作品に特徴的な、煌めくような喪失感が漂う秀逸な一編となっています。作品に描かれているのは文化大革命の時代の在日中国人で、意識の中に部外者としての「異邦人」を抱える彼らの感性の在り処が、ペーソスに満ちた文章で綴られています。
第五世代の監督により中国の新しい局面が世界に広まる
我々が中国にも映画があることを知ったのは、チャン・イーモウ(張芸謀)の『紅いコーリャン』(原題:紅高粱 1987年製作)や、チェン・カイコー(陳凱歌) の『さらば、わが愛/覇王別姫』(原題:覇王別姫 1993年制作)が公開された頃からでした。これらの監督は、文革以降最初の世代の映画製作者たちで、第五世代と呼ばれています。彼らは伝統的な社会主義リアリズムやストーリーテリングの手法を捨て、より自由なアプローチで「閉ざされた国」中国の瑞々しい感性の存在を明らかにし、世界中を驚かせました。
さらに、こちらは返還前の香港映画です。中国の本国映画とは系統が異なるのですが、ウォン・カーウァイ(王家衛)の『恋する惑星』(原題:重慶森林 1994年制作)が公開されると、香港の九龍城の猥雑さと、電脳空間的なイメージともに、中国の感性の新しい局面の出現を世界に知らしめたのでした。
二つの中国映画に見る中国の感性の現在
そして、筆者にとって目から鱗の中国映画が現れます。チアン・ウェン(姜文)の『太陽の少年』(原題:陽光燦爛的日子 1994年制作)と、ダイ・シージエ(戴思杰)の『中国の植物学者の娘たち』(原題:Les Filles du botaniste 2006年制作)です。
太陽の少年
文革時代の首都北京を舞台に繰り広げられる、少年のひと夏の体験を描いた物語です。当時、国家主席毛沢東の指導のもと、都会の青年たちを強制的に地方の農村で働かせ、肉体労働を通じて思想改造をしながら、社会主義国家建設に協力させるという「下放政策」がとられてれていました。下放政策によって大人たちがいなくなったがらんどうの北京で、生き生きと飛び回る少年たち。解放感とノスタルジーに満ちた画面は、これが文化大革命の時代のことか?と、今まで抱いていた文革とその時代の庶民生活へのイメージを一新させるものでした。時代と国は違いますが、そこに描かれた少年たちの無法でヴィヴィッドなパッションは、二・二六事件を時代背景として、会津のピュアな少年たちの喧嘩に明け暮れる日々を描いた、鈴木清順監督の『けんかえれじい』を彷彿とさせます。
ある日、主人公のシャオチュンが忍び込んだアパートで出会った美しい少女の肖像、そして、その少女に街で偶然出会うシーンの恍惚感あふれるカメラワークは、この映画の圧巻です。
中国の植物学者の娘たち
中国雲南省の昆明をモデルとした架空都市・昆林の湖に浮かぶ孤島が、この悲恋物語の舞台です。中国という思想と表現の自由が閉ざされた社会の中の、またさらに外部から遮断された孤島。制限された少ない自由の中でこそ起こる、ピュアでジェニュインな恋愛が描かれています。
孤児院で育った中国人とロシア人のハーフの主人公リー・ミンは、薬草栽培の実習のために孤島の植物園を訪れます。そこで出会った植物学者の娘チェン・アンは、十歳で母を亡くしてからずっと一人で頑迷な父の世話をし続けています。この二人の孤独な魂を持つ女性たちは、いつの間にか互いに惹かれあい、恋人同士となるのでした。
全編に流れる美しい雲南の風景を背景に、二人が辿る悲しい運命が描かれていきます。「私の兄と結婚すれば私たちは一生離れずにいることができる」と、二人の計略で実現したミンとアンの兄との結婚(「私の兄と結婚すれば私たちは一生離れずにいることができる」でしたが、ミンと兄が戯れているところを見て、激しく嫉妬するアン。家を出たアンのあとを追ったミンは、アンに語りかけます。「あなた以外の誰とも決して恋はしない」。ありきたりの言葉でも、このシーンで語られるときには、間違いなく真実の声に聞こえるのです。
監督のダイ・シージエは福建省出身。文革の下放政策において四川省の山村で過ごした経験を持ち、世代的には第五世代にあたります。1984年に政府給費留学生としてフランスに渡り、パリの高等映画学院で学んで以降は、フランスに留まり続けているようです。この映画は、中国本土では当然の如く配給禁止となりました。
中国映画は“感性の輝きの力”を教えてくれる
今、中国は文化大革命の時代には考えられなかったような経済発展を遂げています。改革開放による市場経済への移行で、世界第2位の経済大国にまで上り詰め、社会構造を劇的に変化させてきました。その一方で、言論の弾圧や人権への抑圧がいまだ存在し続けているのも厳然とした事実です。しかし、どれほど抑圧された閉鎖社会の中にあっても、人間の感性が生き生きと輝くのを止めることはできないことを、現代中国映画は表現力によって示しています。