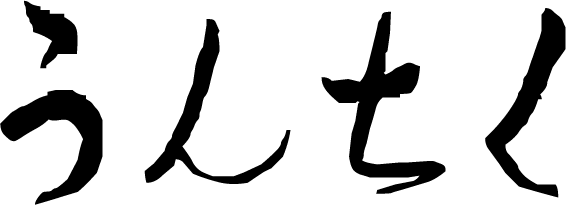2017年度アカデミー賞史上最多14部門ノミネート達成し、ハーバード大学卒のデイミアン・チャゼル監督が6年間構想を練った『ラ・ラ・ランド』。どんなに傑作であっても、記憶に残る映画とは限らない。しかし、この映画は観る者を傍観者で終わらせず、魂に訴えかけてくる。心を装い、偽り、諦めることで、ふさいだ魂の叫びをあぶりだすのだ。枯れた情熱を蘇らせ、観る者の鼓動を突き動かす映画とは何か。ラ・ラ・ランドを通してひも解いていく。
ラ・ラ・ランドの冒頭で、映画『恋に落ちたシェイクスピア』を紹介するナレーションが流れる。この映画の主題は「芝居は真実の恋が描けるか」。シェイクスピアは、役者や作者が詐欺師呼ばわりされた時代において「リアルな心情」を描くことに挑んだ。王族や貴族になりすまし「道化」と呼ばれた男が描く「本物」とは。
本記事を読んで本作に散りばめられた伏線に気付けば、ラ・ラ・ランドの魅力にますますハマることだろう。この映画は劇中の歌詞にもあるように、大人だけでなく若い世代の人々にとっても、壁にぶつかったときに背中を押すきっかけとなる作品である。若いうちから本物をラ・ラ・ランドで体感してほしい。
芝居が魅せる「リアルな心情」は観客との距離をゼロにする
ラ・ラ・ランドを語る上で、外せないのが映画『恋に落ちたシェイクスピア』だ。この作品は、エリザベス女王が芝居小屋に夢中な令嬢に「芝居の作者は恋に無知。美化し、茶化し、あるいは欲情で彩るだけ。芝居は真実の恋が描けるか」と挑発するところから始まる。虚構が暴く真実とは、何なのだろうか。
幼少期の頃から言語に魅了され、言葉の魔力に心を奪われていたシェイクスピアは、言葉を尽くし、愛を描く。シェイクスピア芸術の最大の特徴は、その“リアルさ”だ。リアルの追求は、デイミアン・チャゼル監督も取り入れている。例えば、ノーカットワンテイクによる映画の手法は一発本番の臨場感を生む。カットにより感情の勢いを殺すこともなく、つなぎ目の余地を与えることもない。現実と同じく、一度きりなのだ。
デイミアン・チャゼル監督は「僕が重視したのは、国境を越えて人が共感できる、リアルな心情を語ることだった」と語った。主人公のセブを演じたライアン・ゴズリングは、劇中に代役のバンドマンを一切使わず、自らピアノを奏でた。ブロードウェイではなく、バーで話す声をそのままに、感情を乗せて歌う俳優を主人公に選んだ理由も、リアルに作り込みすぎないバランスを計るためである。
ストーリーの構成が四季からなる
本作は「冬」「春」「夏」「秋」の四季で構成され、根幹には日本の無常感に通じるものがある。シェイクスピアの世代に日本を「気高い島」として伝えたのは、イギリス人のリチャード・ウィルズだ。映画の冒頭でも、セブは車中でジャズアレンジされた「荒城の月」を繰り返し再生し、記憶する。彼の夢は、資金を工面して自分の店を持ち、ジャズピアニストになること。伝統に固執し、過去を渇愛しながらも、ジャズの革命児に憧れるセブ。引き戻せない過去を手繰り寄せるように、同じフレーズを繰り返し弾く。
西洋では永遠に美を見るが、四季を持つ日本においては「移り変わるもの」にこそ美を見る。過去に執着する彼が変わりゆく未来を受け入れたとき、二人の存在以上に大きな愛に気付くのだ。

崖っぷちからの飛躍。人生を台無しにするのは“自分の弱点”ではなく“自分を偽るとき”
セブは、ジョン・レジェンド扮する友人のキースに誘われてバンドのピアノマンになる。しかし、それは心の底からやりたいジャズではなかった。キースがセブに「前の奴よりお前はうまい。でも、偏屈な厄介者だ」と放つ。
シェイクスピアは、人間の唯一の弱点を「黒いほくろ」と呼んだ。人間には、生まれついての黒いほくろがあるという。黒いほくろとは、それさえなければ完全に素晴らしい生涯となるはずなのに、すべてを台無しにしてしまう生来の性癖や弱点のことだ。しかし、人生を台無しにするのは唯一の弱点や性癖ではなく、自分を「偽る」こと。
ヒロインのミアは、物語の中で彼に「本当に好きな音楽かどうか」、人生における重要さを問いかける。唯一の欠点を磨くことは、無類の武器に変えられる可能性を秘めている。まさに、人生を台無しにする性癖や弱点こそが、人生を好転させる最後のチャンスになるのかもしれない。

狂気は勝機を生み出す。大切なのは“過去の失敗にのまれて未来の自分を見失わないこと”
女優になることが夢のミアは、数々のオーディションに落ちる日々を送っていた。6年間オーディションに挑むも叶わず、心が破れてしまう。傷ついた末、最後の可能性を求めて臨んだオーディションで自分について語るよう告げられ、彼女は自らの生い立ちを歌い始めた。
彼女が女優を目指すきっかけとなったのは、映画好きなおばの存在があったから。たとえ何度冷たい水の中へ飛び込むことになっても、おばは笑顔で挑んだ。傍から見れば「狂気」にしか見えない愚かな行為でも、失敗を恐れず熱狂的に挑戦し続けることで、初めて見える景色がある。「狂気」は新しい「色」を見せ、新しい「頂」へと導くのだ。
観客の熱量を最大限に引き出すためには“別れた動機をはく奪すること”
最終的に、セブは店を持ちジャズピアニストとなる。二人が別れた後の5年間は空白となるのだが、これには理由がある。シェイクスピアは大胆な動機の削除という新技法によって、強烈な心理描写に成功した。劇の効果を無限に深め、熱のこもった熱烈な反応を観客からも自分からも引き出すには、主たる要素を一つ取り外せばよい。
効果的な悲劇を生み出すには、どれだけの因果関係で、登場人物にどれほど明白な動機付けが必要となるのか、解くべき謎を作り出すのではなく、戦略的に不透明にするのだ。ありきたりの説明で納得できてしまえば、舞台の持つエネルギーがせき止められてしまう。筋が通った、わかりやすい理由づけを観客に与えなければ、果てしないほど深いところまでいけるのだ。
400年前に「道化」と呼ばれる男が陛下に捧げた真実の恋が、現代に蘇る
シェイクスピア劇における大胆な動機の削除は、ラ・ラ・ランドにも活用されている。セブとミアの5年間が不透明なのは、まさにその効果といえるだろう。不透明さを形成しているのは、シェイクスピアの人生経験と体験からきているものだ。シェイクスピアの実体験からくる不透明さとは「懐疑、つらさ、安易な慰めの拒絶」である。
生きるために、シェイクスピアは「陛下の卑しい俳優」のひとりとして、道化とさげすまれても喜劇役者の道を選んだ。シェイクスピアは「自分は運にも人の眼にも疎まれ、爪はじきにされる身を独り嘆き(中略)顧みて自分の運命を呪った」と語っている。安易な解釈、安易な慰めができないところに映画の底知れぬ熱量があり、観た者を引きずり込んでリアルな心情を体感させるのだ。シェイクスピアの不遇の体験は、セブの目を通して我々に語りかけるようだ。
セブはミアに「きみは優越感のために不遇の俺を愛した」と告げる。二人の関係性が終わるとき、愛は終わりを告げるのだろうか。監督は愛について次のように述べている。
「愛について語るとき、愛自体が主人公の二人よりも大きな存在でなければいけない。僕はそれが美しいと思う」
人は何も所有できない。移りゆくものが美しいのは、そこに普遍を見るからである。