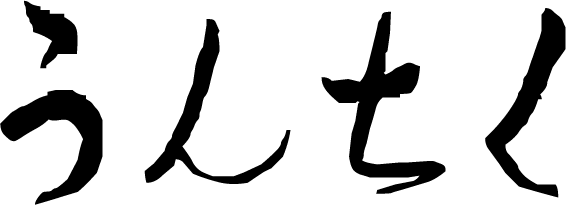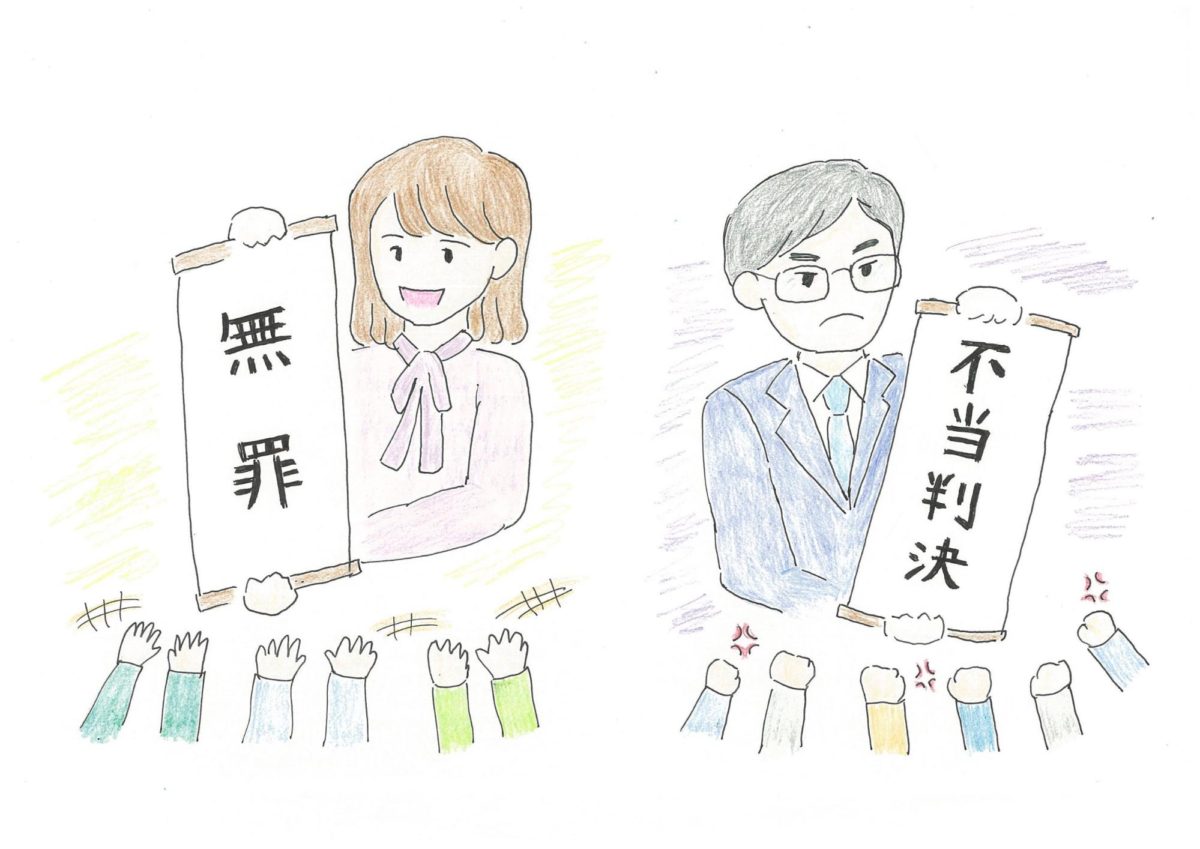突然ですが、みなさんは神社参拝の正しい作法をご存知ですか?神社が大好きな私はよく参拝をするのですが、正しくない作法、NGな所作をしている人をよく見かけます。「折角パワースポットに来ているのに、ちょっともったいないなあ……」と、一人でもどかしくなってしまうこともしばしば。
正しい所作でお参りして、みなさんも神様とよいご縁を結んで欲しい!ということで、こちらでは、知っているようで意外と知らない神社参拝のイロハをご紹介します。
鳥居から手水までの所作・マナー

【1】鳥居の前で一礼
神社にやってきました。鳥居を一歩くぐればそこは神域、ずかずかと入っていくのは失礼にあたります。「お邪魔します」という気持ちで、鳥居に向かってペコリと一礼しましょう。帽子をかぶっている場合は、礼をする前に脱ぐとよいでしょう。
【2】参道は端を歩く
鳥居をくぐったあとはしばらく参道が続きますが、こちらでは歩く位置に注意しましょう。本来参道は神様が通るための道であり、当然神様は中央を通られますので、私たちは端によけて歩かねばなりません。鳥居をくぐる段階で左右どちらかに寄っておくとよいでしょう。このとき、左によけている人は左足から、右によけている人は右足からくぐります。
【3】手水は左手から
しばらく進むと手を洗うところ、すなわち手水があります。これは神様に会う前に、失礼のないように手と口を清めるためのものです。
まずは右手に柄杓を持ち、左手を清めましょう。次に柄杓を持ち替え右手を清め、再度柄杓を右手に持ち左手をコップ代わりにして口をゆすぎます。そのまま左手を清め、柄杓を立てつつ残った水で柄杓の柄を清めて終了です。このとき、お水は汲み替えず、最初に汲んだものを最後まで使いましょう。
ちなみに、なぜ左手から清めるのかというと、日本人は昔から「左手は右手よりも上位」と考えていたから。左右という言葉も左が先に来ており、これはその気持ちのあらわれなのだそうです。
まれに口をすすぐ際に直接口を柄杓につける人がいますが、これはNGです。次に使う人は、きっと「ぎょえーっ」と思ってしまいます。他の人にそんな思いをさせていたら、神様もいい気分はないでしょう。他の参拝客への配慮も忘れずに!
本殿前での所作・マナー

【1】お賽銭は投げ入れない
まずは、お賽銭です。投げたりせず、静かに賽銭箱のなかへ入れましょう。お賽銭は神様という私たちよりも上位の存在に差し上げるものですので、投げ入れるのは失礼にあたります。日常生活のなかでも目上の人に何かを差し上げるときは丁重にしますよね?それと同じ気持ちです。
【2】鈴はそっと鳴らす
続いては、賽銭箱の上につるしてある大きな鈴(本坪鈴)を鳴らします。このとき、がらんがらんと激しくならすのは避けましょう。この鈴は、神様に来訪を知らせるためのもの。言うなれば玄関チャイムみたいなものですので、なるべくそっと鳴らしましょう。
とはいえ、大きく重いので控えめにきちんと音を出すというのはなかなか難しいものです。静かに鳴らすというよりは、「チャイムなので必要以上に鳴らしすぎない」という気持ちで行ったほうがやりやすいと思います。
【3】基本は二拝二拍手一拝
それでは、神様を拝みましょう!ここでの正式な作法は、二拝二拍手一拝です。つまり、二度深い礼をして柏手を二度、手を合わせたまま頭のなかであいさつやお願いごとが終わったら最後に一度深い礼。これで完了です。
多くの神社ではこのやり方で大丈夫ですが、違う作法を正式なものとしている神社もいくつかあります。例えば縁結びで有名な島根県の出雲大社では、二拝四拍手一拝で拝むようにとされています。鳥居から本殿までのどこかに作法を記してある看板があったり、紹介パンフレットやガイドブックに載っていたりもしますので、念のため事前に確認しておくとよいでしょう。
さて、肝心の拝んでいる最中ですが、心のなかでまっさきに自分の住所と名前をお伝えしましょう。神主さんに祝詞をあげてもらう際も名前と住所が読み上げられますし、絵馬などでも名前と住所を書く欄が設けてありますよね。これは、毎日たくさんの参拝者が来るため、きちんと名乗らないと神様もどこの誰だかわからなくなってしまうのだそうです。
神社参拝時の注意点

【1】午後3時以降の参拝は控えよう
参拝は、午後3時までに済ませておきましょう。神社には人だけでなく、浮遊霊なども多く寄ってきます。午後3時以降は徐々に夜に向かっていく時間帯であり、よくないものが増えるのだそうです。参拝はなるべくなら午前中に済ませておくとよいでしょう。ただ、お正月の初詣など、大勢の人がいる場合は夜でも大丈夫とのこと。
【2】神社内のものは持ち帰らない
神社にある石や木は、なんだかパワーを秘めていそうな気がしますよね。その力にあやかろうと思い、持って返ってしまう人も少なくありません。ただ、これは絶対にNGです
前述したとおり、神社は神様の家であり、そのなかにある石や木も神様のものです。勝手に持って帰ってしまうと、それは泥棒と同じことになってしまいます。恩恵にあずかれるどころか、災いのもとにもなりかねません。ある霊能者さんは、靴の裏についた細かな砂もよく落としてから神社をあとにするようです。
もし既に持ち帰ってしまったものがあるなら、速やかにお返しし、丁重にお詫びしましょう。このとき、近くの神社に行くのではなく、必ずもとあった神社にお返ししてください。
【3】お願いをしたらお礼参りもしよう
受験や出産に向けて神社に祈願に行った場合、その後必ずお礼参りに行きましょう。お願いだけしてあとはそのままでは、なんだか心証がよくないですよね。お願いや相談をされた側としては、「あれだけ色々お願いしておいて、お礼も報告もナシかーい!!」という思いを抱きかねません。報告もしつつ、しっかりお礼の気持ちをお伝えしましょう。
神様への敬意を忘れずに

改めて見直してみると、作法の裏には神様への敬意があることがわかります。むしろ、敬意を持たず作法だけ完璧にしても、あまり意味はないと言えるでしょう。
余談ですが……過去に私がとある港町の神社で手水を使おうとしたとき、水のなかに変なものが入っていることに気づきました。それは、食べかけの魚や小動物の内蔵らしきものでした。おそらくは、近くを飛んでいたトンビのごはんだと思われます。私は心のなかで「神様すみません、これ無理なんで勘弁してください!!」とお詫びしながら、手水を使わず参拝させていただきました。極端な例かもしれませんが、無理をしてまで作法にこだわる必要はないと思います。できる範囲で行いましょう。
つらつらと書いてきましたが、いかがでしたか?ほんの少しでもお役に立てればとても嬉しく思います。それでは、みなさんも楽しく爽やかに参拝しましょうね!